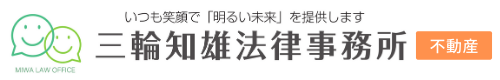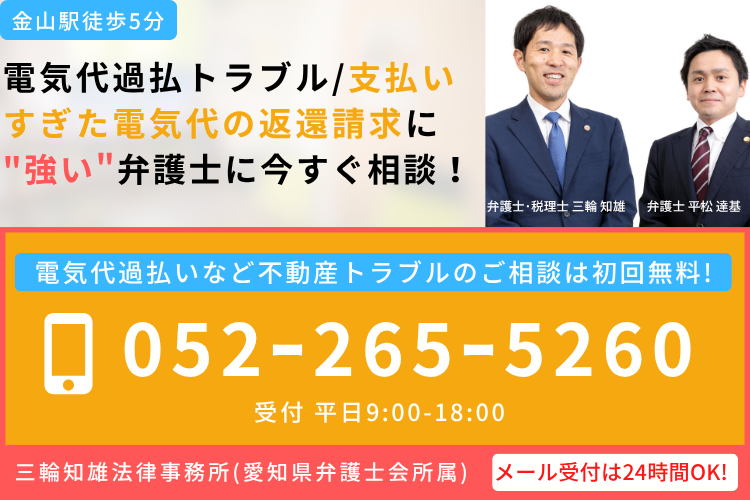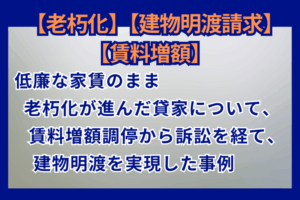【電気代の過払トラブル】【返還請求】ビルのオーナーに対し、余分に支払わされていた電気料金の返還請求訴訟を提起し、過払い分の電気代として300万円の回収を実現した事例
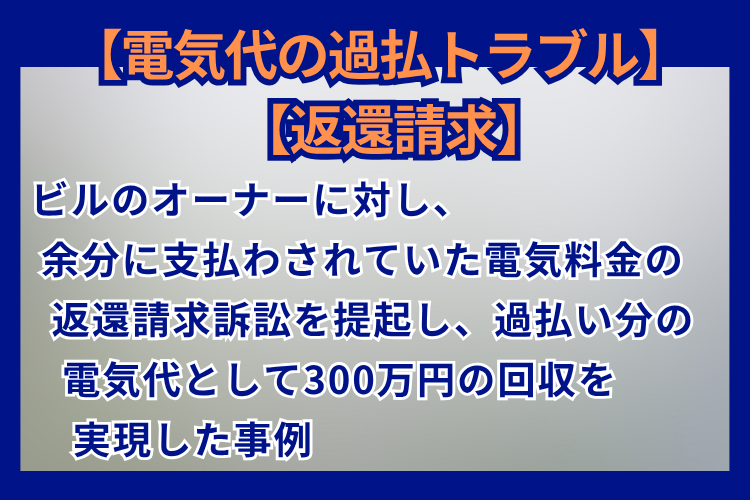
1.相談者の性別、年代、ご要望等
- 借主:法人(製造業)
- 物件:オフィスビル
- 貸主(オーナー):ビルの所有者
- 相談者:法人の代表者(ビルのテナント)
- 具体的なご要望:ビルのオーナーに、余分に支払わされていたと思われる電気料金の返還請求
2.ご相談内容
相談者様は、会社の代表者様です。今年に入り、本社のオフィスを移転しました。
新しいオフィスの、家賃の内訳を見ていて、前に借りていたビルは、管理会社から請求が来る毎月の電気料金が高すぎたように思い、別の名目の金額が含まれていたのではないかと疑問に感じました。そこで、移転前のオフィスの賃貸借契約書を確認したところ、「賃借人は、物件内の電気料金を負担する」という一般的な記載になっておりました。
相談者様としても、電気代については、基本料金と実際に使用した分の電気代を支払うという認識でしたが、請求書は毎月固定の金額となっており、実際には、電気代以外の金額を支払っていることになっていたのではないか、支払いすぎだ電気代を取り戻せないのか、弁護士の見解を聞くため、当事務所へ法律相談にいらっしゃいました。
3.法律相談後の経過
(1)初回無料相談
初回無料相談では、相談者様に、当時の賃貸借契約書や請求書、オフィスの図面等を持参いただきました。また、比較の参考のため、同規模の現在のオフィスでの電気料金の資料を確認しました。
本件については、初回無料相談にて対応しておりますが、頂いた資料のみからでは相手方への請求が成り立つか不明であったため、弁護士による調査のうえ、今後の対応に関する方向性や懸念点等に関する法的な見解を記載した意見書を作成することとなりました。なお、意見書作成費用については、後日、請求を起こす際の着手金の一部に充当という形をとっております。
(2)弁護士による調査・見解の提示
お預かりした資料を下に、弁護士から相談者様に対し、以下の検討内容を意見書として提示いたしました。
- 考えられる請求内容は、賃貸人(建物所有者)に対する不当利得返還請求であること。
- 裁判例等によれば、賃貸借契約書等で、電気料金について特別な費用の支払に関する明確な合意が存在しない場合には、賃借人の負担とすることが相当と考えられる費用のみを賃借人負担としているケースが多いこと。
- 一定の期間より以前の部分については、時効による期間制限が問題となると考えられること。
- 請求の手続について、案件の性質上、訴訟になる可能性が高いこと。
- 弁護士費用の見込み
後日、意見書を検討した相談者様より、当事務所に依頼したいとのご連絡を受け、受任することとなりました。
不当利得返還請求(民法703条、704条)の消滅時効について
消滅時効の期間に関して、新民法の施行日である令和2年4月1日より前に生じた債権については、旧民法が適用され(附則10条4項)、同日以降に生じた債権については、新民法が適用されます。したがって、令和2年3月31日支払分までは、時効期間10年、令和2年4月1日以降支払分は、時効期間5年と考えられます。 ※詳細は法律相談の際に担当弁護士にご確認ください。
(3)ビルのオーナーとの交渉
委任後、弁護士が窓口となり、相手方と交渉を行います。
弁護士及び当事務所のスタッフにて、まず、当時の電力会社が設定していた基本料金を調査し、電気代の過払い額の合計を計算しました。
そして、当時の賃貸人(建物所有者)に対し、電気代の過払い額の返還請求書を内容証明郵便にて、送付しました。
賃貸人側にも弁護士が付きましたが、電気代については、前任のオーナーが請求していた金額をそのまま請求していただけであり、他のテナントについても、同じ基準で電気代を支払ってもらっているため、不当利得には当たらない等と主張し、返還を拒否しました。
(4)不当利得返還請求訴訟
そこで、相談者様と打ち合わせのうえ、不当利得返還請求の訴訟を提起しました。
当方の主張内容
- 相談者様は、賃貸人(建物所有者)に対し、管理会社を介して、電気代として一定の金額(固定額)を毎月支払っていた。
- しかしながら、電力会社が設定していた基本料金を元に算出すると、実際に掛かったとみられる電気代は、1万円~2万円程度である。
- よって、上記の差額に当たる金額について、相談者様としては、賃貸人に対し余分に電気代を支払っていたことになる。
- 電気代の過払い期間は6年以上、過払金額の合計は300万円以上。
賃貸人(建物所有者)の主張内容
- 電力供給にかかる費用として、受電設備の保守費用やメーター検針費用が掛かっており、これらの設備が故障した場合、修理費用が発生する。
- ビルに空き室が発生した場合、当然一室当たりの負担費用が増えるため、その分を負担してもらっていた。
当方の反論内容
賃貸人側の上記主張に対しては、契約書や共益費の金額等をふまえ適切に反論を行いました。
(5)和解成立、解決金の回収
裁判所より、和解勧告がなされることとなり、双方に対し、和解案が提示されました。
和解案の内容としては、一部、相手方の主張を汲んだ部分もあったものの、概ね当方の主張に基づく過払いの電気代の算定となっていました。
最終的には、賃貸人(建物所有者)は、相談者様に対し、約300万円を支払う内容で和解が成立しました。
4.解決までに要した期間と当事務所の弁護士費用
当事務所が解決までに要した期間と弁護士費用は以下のとおりとなります。
解決までに要した期間と弁護士費用
- ご相談から解決までの期間:1年半程度
- 弁護士費用
・ 着手金:約30万円程度(消費税込)
・ 報酬金:約50万円程度(消費税込)
※実費、日当等は別途。
※費用は、あくまで参考としてお示しするものであり、個別の案件やご相談内容によっても異なりますので、詳細は法律相談の際に担当弁護士までお問い合わせください。
5.当事務所の担当弁護士からのコメント

三輪知雄法律事務所
担当弁護士:平松 達基
出身地:名古屋市。出身大学:名古屋大学法科大学院。主な取扱い分野は、建物明渡や立ち退き等の不動産問題、遺留分や遺産分割、企業法務など。
オフィスビルを借りていて、毎月家賃とは別に電気料金を支払っているが、月々の支払額が高額すぎると感じたことはありませんか?
賃貸借契約書では、賃借人は、物件内の電気料金を負担するという一般的な記載になっており、会社としても、電気代については、基本料金と実際に使用した分の電気代を支払うという認識だったが、請求書を見ると、実際の電気料金を上回るベースの固定額となっており、実際には、電気代以外の金額を支払っていることにならないか、支払いすぎだ電気代は取り戻せないか、というご相談を受けることが多くなりました。
支払いすぎた電気代の返還についての三輪知雄法律事務所のサポート
■サポート
この種の案件においては、賃貸人側から、賃借人は長年、請求に従って支払ってきたので、上乗せして支払う合意があった等の主張がなされることがありますが、電気使用量の実額を超える部分が含まれている点について合意や説明がない場合には、賃借人が実額を超える費用を負担することを認識していたものとはいえないと考えられます。
弁護士において、賃貸借契約書、支払っていた電気料金の明細、当時の合意内容、オフィスの面積等をふまえ、過払い分の請求ができるかどうか、調査することができます。
本事案の相談者様のように、過去に借りていたオフィスについて「基本料金と実際に使用した分の電気代を上回る電気料金を支払っていた。取り戻すことはできないか」などお困りのことがあれば、お気軽に当事務所の法律相談(初回無料)をご利用ください。
また、そもそもトラブルにならないために、新しくオフィスの賃貸借契約を結ぶ際、電気料金や共益費等に関する項目を含む契約内容が適切であるかどうか、弁護士に確認を依頼することもおすすめいたします。
6.電気代過払トラブル、支払いすぎた電気代の返還請求に強い弁護士へのお問い合わせ
「電気代トラブル、支払いすぎた電気代の返還請求に強い弁護士」へのお問い合わせは、以下の「電話番号(受付時間・平日 9:00~18:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
※この記事は公開日時点の法律をもとに作成しています。
※個人情報保護及び争点の理解等の観点から、結論に影響がない範囲で事案の一部を変更している場合があります。